roy > naoya > 情報リテラシーII > (1)プレゼンテーション[1]-基本操作
(1) プレゼンテーション[1]-基本操作
[1]プレゼンテーションソフトとは
- 会議などで説明を行い、相手に理解してもらったり説得したりすることをプレゼンテーションと呼ぶ。プレゼンテーションを行う際には何らかの資料を提示することが多い。従来はOHPが使用されていたが、現在ではコンピュータを用いて資料を提示するプレゼンテーションが主流となっている。
- プレゼンテーションの資料を作成するソフトをプレゼンテーションソフトと呼ぶ。Microsoft PowerPoint(パワーポイント)は代表的なプレゼンテーションソフトとして広く利用されている。同等の機能を有するLibreOffice Impressも利用されるようになってきている。
- OHPとは異なり、パワーポイントをはじめとするプレゼンテーションソフトでは動画を扱うことができる。また、スライドを作成するのみでなく、配布資料や発表者向けの手元資料も作成可能である。
[2]プレゼンテーションの組立て
いきなりプレゼンテーションソフトで作り始めない。いきなりスライドを作成すると次のような問題が生じやすい。
- デザインがプレゼンテーションソフトのレイアウトに依存する。具体的には箇条書きで文章ばかりのスライドになってしまいがち。箇条書きは通常の文章よりは読みやすいがベストではない
- 自分が作りたいスライドを作って満足するが、話の流れができておらず聞き手は何を言いたいのか理解することができない
- ストーリーは組み立っているが、聞き手には興味がない内容であり聞いてもらえない
自分が話したいことは聞き手が聞きたいことであるとは限らない。聞き手に興味を持って聞いてもらうためには、以下の流れでプレゼンテーションを組み立てる必要がある。
- テーマを決める
- 話をしたいテーマを決めよう。この時点では「自分の出身地について」とか「コーヒーについて」「TPPについて」など漠然とした内容で構わない。今回は「ギャップイヤープログラムについて」。
- 聴衆を分析する
- 聴衆の属性や人数、興味・関心(興味あり、強制的に参加されられている等)、事前知識(知識なし、多少は知っている、専門用語まで理解している)などによりプレゼンテーションの進め方は異なる。
- 興味がない人が多いなら最初に面白い話をして、関心を持ってもらえればそれだけで成功かもしれないし、興味を持っている人が多いならば、より専門的な話をして内容を理解してもらうのが良いかもしれない。同じテーマでも聴衆の属性によって話す内容は変化するべきであると考えること。
- 結論を決める
- 聴衆を分析したら、今回の聴衆に対して何を伝えるかを考えよう。ギャップイヤーのプログラムにおいて自分自身が行った活動を伝えるのが良いだろうか。自分の意識の変化を中心に語るのが良いだろうか。身についた知識について語るのが良いだろうか。
- プログラムを通して、「業界の知識が増えた」「自分のスキルが向上した」「今後学ぶべき課題が明確になった」等、様々な結論がある。どのような結論を述べたいのかによって、話す内容は異なってくる。まずは最終的に言いたいことを整理しよう。
- 発表の構成を考える
- ギャップイヤープログラム自体は最初に教員から概要を説明する。実習先の概要や実習の目的、スケジュールなどから話すとよい。
- アナログで作成する
- 付箋や4コマノートを準備し、作成するスライドのイメージを書いてみよう。イメージなくプレゼンテーションソフトで作ろうとすると、デフォルトのレイアウトに依存したありきたりなスライドしか作れない。以下のスライドはどちらが関心のない聴衆の注意を引くか、また関心のある聴衆にとって有効なのはどちらかを考えてみよう。
- 発表時の心得
- その場は分かりやすかったと思っても次の日になったら忘れてしまうプレゼンテーションより、記憶に残るプレゼンテーションを行うことができるようにしよう。そのためには画像を上手く活用すると良い。
- プレゼンテーションに関する本を読むと、「聴衆はスライドを見に来たわけではないので話が重要だ」という本と、「話よりもぱっと見て分かるスライドを作ることが重要だ」という本に分かれる。一見矛盾するようだが、プレゼンの目的や聴衆によりプレゼンテーションの方法はいくらでも変化する。今回取り上げる方法が唯一の方法ではないことに注意しよう。
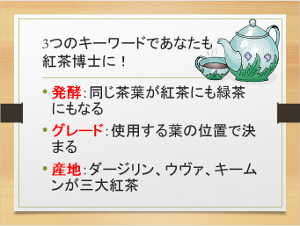

[3]発表会の概要
大正大学地域創生学部の1年生と本学セミナーハウス(吹浦)にて合同発表会を行う。 地域創生学部は1年次と3年次の第3クォーターに全学生が2か月間の地域実習を行う。2年次には、1年次の実習先について東京で関心を持ってもらうための取り組みを実施している。今回は山形県最上町で地域実習を行っている1年生(7名:男5、女2)と相互発表を行う。先方の想定するテーマは以下の通り。
- 最上町地域資源マップ作成(水資源マップの完成):最上町の自然、歴史・文化、産業などの地域資源を紹介するマップを作成する。また、2017 年度に調査した湧水等の自然水について再度確認調査を行い、最上町役場および町民のニーズに応える形で完成させる。
- 森林の維持、林業の振興と木質エネルギーの利用に関する学修:最上町における森林の維持、林業の振興および木質バイオマス・エネルギーの利用について学修を行い、最上町のアイデンティティとなっている「森とともに生きる」土地柄を観光・産業両面において利用する方法について考える。
- 温泉地活性化:瀬見温泉の現状を把握し、学生の視点からソフト面を中心とした活性化の提案を考える。旧・瀬見小学校校舎の利活用状況も視野に入れる。
- 東法田地区の理解と将来像構想:最上町東法田地区の住民から地区の特色と魅力を学び、将来像を考える。2017 年度の月楯・萱場地区、2018 年度の満沢地区における調査結果との比較等も行い、東法田地区の住民の意向や課題意識に寄り添った構想を行う。
夜はバーベキューを実施し、セミナーハウスに宿泊。
タオル、シャンプー、歯ブラシ等のアメニティは持参する。ドライヤーも持参。
[4]本日の作業
- s4にアクセスし、自分自身の発表テーマについて聴衆分析を行い、結論を明確にする。s4に記載する項目は以下の通り。
- 人数
- 年齢層
- 会場の広さ(スライドの字の大きさに関連)
- 聞き手の発表会への関心(自主参加、強制参加等)
- 聞き手の知識量(テーマに関連して何を知っていて、何を知らないか)
- 聞き手との関係
- 聞き手が聞きたいこと(聞き手も学外学修を実施していることを踏まえて考えよう)
- これらを踏まえてあなたが伝えるべきこと
- スライドデザインの考え方(写真中心でイメージを伝える/文字中心で細部を伝える等)
- 4コマノートを使って、スライド作成イメージを考える